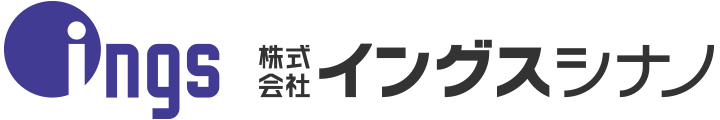メールマガジン6月
今回のお題はChatGPT(Generative Pre-trained Transformer; 生成可能な事前学習済変換器)についてです。
当社の事業と直接かかわりがあるがどうか少し疑問ですが、巷で話題のChatGPTについて少し調べてみました。
ネットに掲載されていた例ですが、ChatGPTに「自動車業界向けのAIニュースに関するメールマガジンを作ってください」と入力したところ、タイトルも含めて次のような文章が即座に生成されたとのこと。
「こんにちは。AIの最新ニュースをお届けする『AIのマガジン』です。
今回は、自動車業界でのAIの活用方法をご紹介します。
AI(人工知能)は、コンピューターが人間と同様に学習や思考を行うことができる技術です。自動車業界では、AIを採用することで、自動運転車の実現や、車両のセンサーやカメラで収集されたデータをもとにした予測分析などが可能になります。
例えば、自動運転車においては、AIを使用することで、車両が自動的に道路を走行し、交差点での停止や左折などをおこなうことができます。また、車両のセンサーやカメラで収集されたデータをもとにした予測分析により、車両の故障やアクセスの予測ができるようになります。
さらに、AIを使用することで、自動車の生産プロセスや品質管理などにも活用されています。
今後も、AIに関する最新ニュースや、自動車業界での活用事例をお届けしていきますので、お楽しみに!」
実際、お読みになっていかがでしょうか。正直、ほとんど違和感は感じません。ChatGPTは「オリジナルのテキストを生成することができる人工知能ツール」で、OpenAIという会社が開発したものです。すでにアクティブユーザーは2か月間で1億人に達しており、TikTokやInstagramが1億人に到達するのにかかった期間がそれぞれ9か月と2年半だったのに対して、史上最速だそうです。
ChatGPTは対話型のサービスであり、質問に答えてもらうことも、詩や歌、エッセイ、短編小説などを書いてもらうこともでき、特定のテストに対して、人間と同水準以上の回答を行うこともできるとされています。将棋や囲碁の世界では、すでにAIがトッププロを超えていますが、従来は難しいとされていた感情表現とか芸術的創造という人間独自の特徴まで、いよいよ踏み込んできたということでしょうか。すごく面白くて大ヒットした小説が、実はChatGPTが書いたというようなことも、もはや空想ではありません。
上記のような途方もない能力を有していることから、ChatGPTが持つリスクについて多くの識者が見解を述べています。例えば、教育現場において生徒がChatGPTで生成した論文を提出してきたらどうするか。ChatGPTが参照する元の記事についての著作権は保護されているか。あるいは、会社の機密情報を入力してしまったらどうなるのかなど、これから使用についてのルールを決めていかなければならないというのが実態のようです。
これまでは、なにかわからないことがあれば、Googleで検索して知識や情報を取り込み、それに自分のアイディアを追加して解決していくというのが手順でしたが、ChatGPTはそのアイディアの部分も提案してくれるということでしょうか。
今回のメールマガジンはもちろんChatGPTによる生成ではありませんが、機会があれば、「テーマだけインプットしてどのような返事が返ってくるか」やってみたいような気もします。