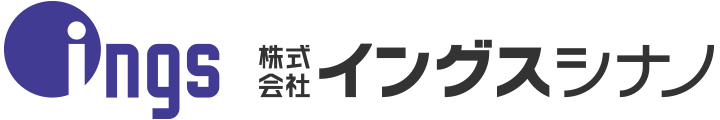メールマガジン 4月
今回のお題は『Webマーケティング』についてです。
商品やサービスの売買や取引のやり方などがずいぶん変わって、それに伴ない私たちの生活や仕事のやり方自体も大きく変化しています。先日「全国的に書店が減少している」というニュースがありましたが、本屋に行って興味がある本を物色するというような生活スタイルはすでに昭和の遺物なのかもしれません。
さて、「Webマーケティング」とは、Webサイトに人々の関心を呼び込んで、そのWebサイトに掲載された商品やサービスの販売、さらにブランディングを促すためのマーケティング(活動)とされます。私たちの事業においても、潜在的なお客様がどうやって、どのタイミングで新規発注先の情報を探しているのかを把握したうえで、適切なネットワークにタイムリーに技術情報や特長などを流していかなければなりません。
あるアンケートによれば、「ユーザーとして製品を探す際、どのような媒体を利用するか(複数回答)」という質問に対し、Googleなどの検索エンジンを利用するという回答が75%、企業のWebサイトが60%、メーカーからのメールマガジンが30%というような傾向になっているようです。実際、私たち自身も新しい取引先を探すときは、まず、Googleで検索し、メールでコンタクトをとります。また、実際に訪問する場合は、事前にGoogleマップで相手のオフィス場所を確認して出かけるというような行動パターンが普通です。
新市場開拓においてポイントになるのは、お客様が発注を考えているタイミングでタイムリーにマーケティング活動ができるかどうかという点になります。どんなに商談の機会を増やしても、お取引先が発注のタイミングでなければ、受注につなげることは難しいわけです。この発注のタイミングを捉えるという観点で、Webマーケティングはとても有効と言われています。つまり、こちらからお取引先を見つけるというのではなく、お取引先に自分たちを発見していただくという逆転の発想です。たしかに、探していただくということは、発注をしたいというニーズがあるわけですので、タイミングは合致します。
ということで、私たちもホームページの充実やタイムリーな更新に力を入れています。特に、技術資料については頻繁にアップしていきますので、ぜひご覧ください。また、Google検索においてはキーワードが重要ですので、自社が得意とする技術等について適切なキーワードが掲載されているかというような分析もおこなって、皆さまがアクセスしやすいように工夫してまいります。
この時期は卒業や入学、入社など多くの人々が区切りを迎える季節です。当社にも4月1日に新人2名が入社します。4月2日は新しい2024年度のキックオフを行って、会社全体のベクトルを合わせて頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
(T)